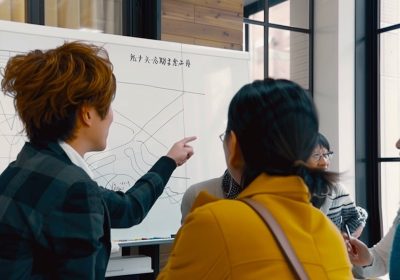山と海のあいだに:新潟の地形が育む人間模様
佐渡の朝は、海の向こうから昇る太陽と、背後にそびえる大佐渡山地の稜線が織りなす光と影から始まる。
私がこの島に住み始めて幾星霜、毎朝窓を開けるたびに思うのは、この土地が持つ特別な位置についてだ。
新潟本土から34キロメートル離れた日本海に浮かぶ佐渡島は、まさに「山と海のあいだ」に存在している。
そしてこの地理的な特性こそが、この土地に暮らす人々の心性や文化を深く規定してきたのではないかと感じている。
「風の向きと、暮らしの匂いを感じること」
これが私の取材哲学であり、地形を読み解く鍵でもある。
記者時代から取材を重ねてきた新潟の各地でも、同じような光景に出会ってきた。
山脈と海岸線が複雑に交差するこの地域では、地形そのものが人々の営みの舞台装置となり、独特の人間模様を育んでいる。
この記事で出会うのは、自然と共に生きる人々の静かな営みである。
風の向きを読み、潮の満ち引きに合わせ、雪の重さを知り抜いた人々が、この土地でどのような暮らしを紡いできたのか。
地形が語りかける物語に、しばし耳を傾けてみたい。
山と海に囲まれた新潟の地形的特徴
新潟県の地形を俯瞰すると、まさに日本列島の縮図ともいえる複雑な構造が浮かび上がってくる。
県域の大部分がフォッサマグナという地質学的に重要な地域に位置し、この地形的特性が県全体の自然環境と文化的基盤を決定づけている。
新潟県の地形を構成する主要な要素を整理してみよう。
- 山地部:朝日山地、飯豊山地、越後山脈、飛騨山脈の一部
- 平野部:越後平野、高田平野、柏崎平野などの沖積平野
- 海岸部:総延長634.7キロメートルの変化に富んだ海岸線
- 島嶼部:佐渡島(854.81㎢)と粟島を含む離島群
これらの地形要素が相互に作用し合い、新潟県独特の気候や生態系を生み出している。
東から南にかけて標高2000メートル級の山々が連なり、まるで巨大な城壁のように県土を取り囲んでいる。
これらの山々は単なる地形上の特徴ではない。
日本海からの湿った空気がぶつかる壁となり、この地域特有の気候を生み出す重要な役割を担っている。
一方、西側に広がる日本海は、季節によって全く異なる表情を見せる。
夏の穏やかな青い海が、冬になると荒々しい波濤となって海岸を打つ。
佐渡島の成り立ちと独自性
佐渡島は、新潟県の地形的特徴を最も象徴的に表現している場所である。
面積854.81平方キロメートルのこの島の形状は、実に興味深い特徴を持っている。
| 特徴 | 表現 | 意味 |
|---|---|---|
| 全体の形 | カタカナの「エ」 | 三つの地形区分を示す |
| 海岸線 | アルファベットの「S」 | 複雑な入り江構造 |
| 山地配置 | 雷マーク「⚡」 | 南北の山地の位置関係 |
この島の地形構造は、大きく三つの区分に分けられる。
北部の大佐渡山地は標高が高く、最高峰の金北山(1,172メートル)を有している。
南部の小佐渡山地は比較的なだらかな丘陵地帯で、最高標高は大地山(645メートル)である。
そして、この二つの山地の間に広がる国中平野は、離島の平野としては珍しく広大な面積を持ち、水稲栽培の中心地となっている。
興味深いのは、この島がもともと二つの島がつながって形成されたという地質学的な背景だ。
激しい火山活動の痕跡が今でも島の各所に残されており、大昔の海底噴火の名残を物語っている。
大佐渡山地の北側では、山が海岸のすぐそばまで迫り、断崖絶壁と無数の岩礁が約50キロメートルにわたって連なる。
中でも尖閣湾の景観は圧巻で、荒波の浸食によって削られた奇岩群が海上に点在している。
山脈と海岸線が交差する風土
新潟県本土の海岸線は、その変化の豊かさで知られている。
総延長約635キロメートルに及ぶこの海岸線は、地形の成り立ちによって大きく異なる表情を見せる。
代表的な海岸地形を北から順に挙げてみよう。
- 1. 笹川流れ(村上市):花崗岩の隆起による奇岩海岸
- 2. 新潟海岸:砂丘地形による長大な砂浜海岸
- 3. 角田・弥彦海岸:枕状溶岩による特異な岩石海岸
- 4. 寺泊・出雲崎海岸:段丘地形による変化に富んだ海岸
- 5. 親不知・子不知海岸(糸魚川市):北アルプス直下の断崖海岸
特に印象的なのは、糸魚川市の親不知・子不知海岸である。
ここでは北アルプスが日本海に直接落ち込む断崖絶壁が約10キロメートルにわたって続いている。
古来より北陸道屈指の難所として知られ、「親は子を忘れ、子は親を顧みる暇がない」ほどの険しさからその名が付けられた。
この地形的特性は、交通史や文化交流史にも大きな影響を与えてきた。
松尾芭蕉や伊能忠敬をはじめ、多くの文人墨客や旅人がこの難所を通過し、その体験を記録に残している。
季節ごとに変化する地形の表情
新潟県の地形は、四季を通じて劇的にその表情を変える。
この季節変化の激しさは、日本海側気候の特徴と山地の影響が相まって生み出される現象である。
春
雪解けとともに山々から豊富な水が流れ出し、平野部の田んぼに水が張られる。
この時期の越後平野は、まるで巨大な水鏡のような美しさを見せる。
弥彦山の雲の動きを見て天気を予測する地元の知恵も、この季節の特徴的な風景の一つだ。
夏
日本海側特有の好天に恵まれ、山々の緑と海の青が鮮やかなコントラストを描く。
海岸部では多くの海水浴場が賑わいを見せ、特に佐渡や本土の海岸は水質の良さで知られている。
山間部では高山植物が美しい花を咲かせ、登山者や自然愛好家を魅了する。
秋
山々は燃えるような紅葉に彩られ、平野部では黄金色に実った稲穂が風に揺れる。
清津峡渓谷の紅葉は特に有名で、柱状節理の岩肌と清流、V字形の峡谷美が織りなす景観は圧巻だ。
冬
この季節こそが新潟県の地形的特徴を最も象徴的に表現する時期である。
日本海側特有の冬型の気圧配置により、西または北西からの強い季節風が山々にぶつかり、大量の雪を降らせる。
山間部では数メートルに及ぶ積雪となることも珍しくなく、この雪が地形そのものを一変させる。
雪に覆われた地形は、単に白い景色というだけでなく、人々の生活様式や文化的活動に根本的な変化をもたらす。
地形が形づくる暮らしと文化
地形は単なる自然環境ではない。
そこに住む人々の暮らし方や文化の形成に、決定的な影響を与える重要な要素である。
新潟県の多様な地形は、それぞれ異なる生活文化を育み、独特の人間模様を生み出してきた。
私が各地を取材して歩く中で気づくのは、地形に根ざした知恵や工夫が、単なる生活技術を超えて、その土地の精神性や価値観の基盤となっていることだ。
地形と文化の関係を体系的に整理してみると、以下のようなパターンが見えてくる。
| 地形タイプ | 主な生活文化 | 代表的な知恵・技術 |
|---|---|---|
| 山間部 | 雪国文化 | 雁木建築、雪室保存、雪下ろし技術 |
| 平野部 | 稲作文化 | 灌漑技術、水田管理、米作文化 |
| 海岸部 | 漁業文化 | 漁撈技術、塩作り、海産物加工 |
| 島嶼部 | 海洋文化 | 航海術、島内交通、文化保存 |
これらの文化は互いに影響し合いながら発展し、新潟県独特の複合的な文化圏を形成している。
山間の集落:雪と共に暮らす知恵
新潟県の山間部に点在する集落を訪ねると、雪国ならではの暮らしの知恵に出会うことが多い。
冬になると数メートルの雪に埋もれてしまうこれらの集落では、雪を敵視するのではなく、むしろ生活の一部として受け入れる文化が育まれてきた。
雪国の建築技術として最も注目すべきは「雁木」である。
- 雁木の構造:軒下を延長した通路空間
- 雁木の機能:雪や雨を避けながらの移動が可能
- 雁木の特徴:私有地でありながら公共的役割を担う
- 雁木の現存地:上越市高田、阿賀町津川など
上越市高田の雁木は総延長約16キロメートルにも及び、世界最長の雁木として知られている。
この建築様式は、個人の負担で公共の利便を図るという、雪国独特の共同体精神の表れでもある。
雪下ろしの技術も、代々受け継がれてきた重要な生活技術の一つだ。
タイミングを間違えれば家屋の倒壊にもつながりかねない雪下ろしは、単なる作業ではなく、雪の性質を熟知した職人技といえる。
雪の種類を見分け、気温や湿度を考慮し、屋根の構造を理解した上で行われる雪下ろしは、まさに地形と気候に適応した技術の粋である。
雪を活用した食文化も興味深い。
雪室を利用した野菜の保存は、電気を使わない自然の冷蔵庫として機能し、野菜の甘みを引き出す効果もある。
雪の下で発酵させる漬物や、雪解け水を使った酒造りなど、雪を積極的に活用した食文化も発達している。
漁村のリズム:海がもたらす日常
新潟県の海岸線に点在する漁村では、日本海の恵みと共に生きる独特のリズムが刻まれている。
私が佐渡や本土の漁村を取材する際にいつも感じるのは、海が単なる仕事場ではなく、生活そのものの基盤となっていることだ。
漁師たちが日々向き合う自然の兆候を列挙してみよう。
- 朝の気配:夜明け前の空気の動きや色合い
- 風の向き:風向きの変化が示す天候の予兆
- 雲の動き:雲の形状や移動速度による気圧配置の読み取り
- 波の高さ:うねりの周期や波高による海況の判断
- 潮の満ち引き:潮汐表と実際の潮位の微妙な差異
これらの自然の兆候を総合的に読み取り、その日の漁業活動を決定する技術は、現代の気象予報技術が発達した今でも重要な役割を果たしている。
佐渡の漁村では、島という地形的制約が逆に独特の漁業文化を生み出している。
外海と内海では魚種も漁法も異なり、季節に応じて漁場を変える必要がある。
「佐渡は小さな島だが、海の表情は実に多様だ。真野湾の穏やかな波と、外海府の荒波では、まるで別の海のようだ。」
―両津の漁師・佐藤さん(取材時70歳)
真野湾や両津湾では穏やかな内海を活かしたカキの養殖が盛んで、外海では回遊魚を狙った定置網漁業が主体となる。
加茂湖は新潟県最大の湖でありながら汽水湖という特殊な環境で、ここでもカキ養殖が行われている。
このような多様な水域を持つ佐渡では、漁師たちは複数の漁法を使い分ける技術が要求される。
島の祭りと伝統芸能:風土が育む精神性
佐渡島の祭りや伝統芸能を語る際に欠かせないのが、島という地形的制約が生み出した独特の文化的融合である。
この島には三つの異なる文化的要素が流入し、島という閉鎖的な環境の中で独特の形で融合している。
佐渡の文化的基盤となった三つの要素を整理してみよう。
- 1. 貴族文化:流罪によって持ち込まれた宮廷文化の系譜
- 2. 武家文化:金銀山の発展とともに江戸から移植された文化
- 3. 町人文化:北前船によって運ばれた商業都市の文化
この文化的融合の最も顕著な表れが、島内約120地区に存在する鬼太鼓の多様性である。
鬼太鼓は集落の厄を払い、五穀豊穣や大漁、家内安全を祈って舞われる佐渡独特の芸能で、踊りの型は5つの流派に大別される。
しかし、同じ型でも集落によって微妙に異なる特徴を持ち、一つとして同じものはない。
これは島という地理的制約の中で、各集落が独自の発展を遂げてきた結果である。
能楽の普及も佐渡の地形的特性と深く関わっている。
かつて島内に200ほどあったとされる能舞台のうち、現在でも35棟が現存している。
これは全国の能舞台の約3分の1にあたる数で、能楽が庶民レベルまで深く浸透していたことを物語っている。
「鶯や十戸の村の能舞台」と詠まれたように、農作業をしながら謡曲を口ずさむ日常風景が、島のあちこちで見られたという。
島という閉鎖的な環境が、外部から持ち込まれた高度な文化を大切に保存し、独自の発展を遂げさせる温床となったのである。
人々の声に耳を澄ます
地形が人間の暮らしに与える影響を理解するには、実際にそこで生活している人々の声に耳を傾けることが不可欠である。
私が長年にわたって取材を続けてきた中で出会った人々の言葉には、地形と人間の関係の本質を物語る深い洞察が込められている。
取材の際に必ず心がけているのは、「風の向きと暮らしの匂いを感じること」である。
これは単なる感覚的な表現ではなく、地形が生み出す微細な環境の変化を、そこに住む人々がどのように感じ取り、生活に活かしているかを理解する手がかりなのだ。
地元の語り部たちの記憶
佐渡の小さな集落で出会った古老たちの話には、地形に関する豊富な知恵が込められている。
彼らの記憶の中には、現代の気象観測技術では捉えきれない、土地固有の気候や地形の特徴が蓄積されている。
相川の元鉱山労働者・田中さん(当時85歳)は、こう語ってくれた。
「昔は金山の煙突から出る煙の向きで、その日の天気を予想したもんだ。煙が真っすぐ上に立つ日は凪で、海も穏やか。煙が北に流れる日は南風で、必ず雨が降った。山の地形が風の通り道を作っているんだね。」
このような観察眼は、長年その土地で生活してきた人々だからこそ身につけることができる貴重な知恵である。
両津の漁師・佐藤さん(当時70歳)の言葉も印象的だった。
「加茂湖の水位を見ると、その年の雪の降り方がわかる。山の雪解け水が湖に流れ込むから、雪の多い年ほど湖の水位が上がる。湖の水位が高い年は、カキの生育も良い。すべてつながっているんだ。」
彼らの話から浮かび上がってくるのは、地形という自然環境と人間の生活が密接に結びついた世界観である。
現代の私たちが忘れがちな、自然と人間の有機的な関係がそこには息づいている。
「風の向きと暮らしの匂い」から見えるもの
私の取材哲学である「風の向きと暮らしの匂いを感じること」は、地形が人々の暮らしに与える影響を理解する上で重要なアプローチである。
風向きの変化は、その土地の地形的特徴を反映している。
新潟県の各地域には、地形に起因する特有の風の性質がある。
地域別の特徴的な風を整理してみよう。
| 地域 | 特徴的な風 | 地形的要因 | 生活への影響 |
|---|---|---|---|
| 下越 | 荒川だし、安田だし | 越後山脈から日本海への谷筋 | 農作業の時期決定に影響 |
| 上越 | 蓮華おろし | 妙高山系からの吹き降ろし | 雪質や積雪量に影響 |
| 佐渡 | 潮風 | 島特有の海洋性気候 | 塩害対策や農作物の品種選択 |
これらの風の特性を理解することで、その土地の人々がどのような工夫や対策を講じているかが見えてくる。
「暮らしの匂い」とは、その土地独特の生活文化が醸し出す雰囲気のことである。
山間部の集落を訪れると、雪に対する備えや工夫が生活の随所に表れている。
家屋の構造、道具の使い方、食べ物の保存方法、近所付き合いの仕方まで、すべてが雪国という地形的特性に適応している。
海岸部の漁村では、潮の満ち引きに合わせた生活リズムが根付いている。
朝の出漁時間、網の手入れ作業、魚の出荷時期など、すべて海の条件に左右される。
若者たちの視点:地形と向き合う新しい生き方
近年の取材で特に印象深いのは、若い世代が地形的特性を活かした新しい生き方を模索していることである。
彼らは伝統的な知恵を受け継ぎながらも、現代的な視点や技術を取り入れて、地形との関わり方を再構築している。
佐渡でトキの野生復帰活動に取り組む研究者の山田さん(30代)は、名古屋から移住してきた。
「佐渡の地形の多様性に驚いています。山あり谷あり、海あり湖あり。これだけ多様な環境が小さな島に凝縮されているからこそ、トキのような生き物が生息できるんです。地形の多様性が生物の多様性を支えているんですね。」
彼の研究活動は、佐渡の地形的特性を科学的に活用した現代的な取り組みの一例である。
新潟市でサーフィンを楽しむ伊藤さん(20代)は、日本海の特性を活かしたマリンスポーツの可能性について語る。
「新潟の海は、太平洋側と比べて干満の差が少なく、初心者でも始めやすいんです。地形的にも、砂浜が多くて安全。これからもっと多くの人に新潟の海の魅力を知ってもらいたい。」
彼らの活動は、地形の特性を現代的な価値観や技術と組み合わせることで、新しい地域の魅力を創出している。
また、山間部では雪を活用した新しいビジネスも生まれている。
雪室を利用した野菜の貯蔵ビジネスや、雪を使った夏季のイベント開催など、雪国の地形的特性を逆手に取った取り組みが注目されている。
これらの事例は、地形という自然環境が制約ではなく、むしろ可能性の源泉となり得ることを示している。
若い世代の柔軟な発想と、地域に蓄積された伝統的な知恵が融合することで、新しい地域文化が生まれつつある。
地形とともにある未来
地形は過去から現在へと続く物語の基盤であると同時に、未来に向けた可能性の源でもある。
新潟県の多様な地形は、これまで様々な自然災害の脅威をもたらす一方で、豊かな文化や産業の基盤となってきた。
これからの時代において、地形との付き合い方はどのように変化していくのだろうか。
私が各地で出会った人々の取り組みから見えてくるのは、地形の特性を深く理解し、それを活かした持続可能な地域づくりの姿である。
現代の技術や価値観と、伝統的な知恵を融合させながら、地形とともに歩む未来の道筋が模索されている。
自然災害と共存する知恵
新潟県は、地形的特性により様々な自然災害のリスクを抱えている。
しかし、長年にわたってこの土地で暮らしてきた人々は、災害を完全に防ぐのではなく、被害を最小限に抑えながら共存する知恵を培ってきた。
主要な自然災害とその対策を整理してみよう。
- 1. 雪害:豪雪による交通麻痺、雪崩、建物損壊
- 2. 地震災害:フォッサマグナ地帯特有の地震活動
- 3. 洪水災害:梅雨や台風による河川氾濫
- 4. 土砂災害:地すべりや土石流の発生
2004年の新潟県中越地震は、これらの災害が複合的に発生する「複合災害」の典型例だった。
地震による建物被害に加えて、大規模な土砂崩れや液状化現象が発生し、その後の豪雪がさらなる被害をもたらした。
この経験から学んだ教訓は、単一の災害対策ではなく、地形の特性を踏まえた総合的な防災対策の重要性である。
地域の人々が培ってきた災害との共存の知恵は、現代の防災技術と組み合わせることで、より効果的な災害対策となる。
雪国で発達した雁木の技術は、現代の都市計画にも応用できる知恵である。
また、地すべり地帯における棚田の造成技術は、土砂災害の軽減にも役立っている。
地形を活かした地域再生の試み
近年、新潟県各地で地形の特性を活かした地域再生の取り組みが注目されている。
これらの試みは、単に経済的な活性化を目指すだけでなく、地形と人間の関係を再構築する文化的な意味も持っている。
代表的な取り組みを紹介してみよう。
佐渡のトキ野生復帰プロジェクト
佐渡の多様な地形環境を活かして、トキの野生復帰が進められている。
里山の棚田、加茂湖の湿地、海岸部の干潟など、様々な地形が提供する生息環境の多様性が、トキの繁殖と定着を支えている。
このプロジェクトは、地形の保全と生物多様性の回復を同時に実現する先進的な取り組みとして国際的にも注目されている。
雪国観光の新しい形
十日町市や魚沼地域では、豪雪地帯という地形的特性を観光資源として活用する取り組みが進んでいる。
「大地の芸術祭」では、雪国の地形や景観をアート作品と融合させ、新しい文化的価値を創出している。
また、雪を利用した食品保存技術「雪室」は、農産物のブランド化にも貢献している。
海岸地形を活かしたマリンツーリズム
笹川流れや親不知海岸では、特異な地形景観を活かした観光開発が行われている。
遊覧船による海上からの景観鑑賞や、地質学的な価値を伝えるジオツーリズムなど、地形そのものを観光資源とする取り組みが拡大している。
これらの地域再生の試みに共通しているのは、地形を制約として捉えるのではなく、独自の価値を持つ資源として活用する発想である。
外からの視点と内からのまなざしの交錯
地形との関係を考える上で興味深いのは、外部から来た人々の視点と、地元で生まれ育った人々のまなざしが交錯する場面である。
私自身も佐渡に移り住んだ「外部者」として、この交錯を日々実感している。
外部から来た人々が新潟の地形に対して抱く印象と、地元の人々が当たり前と思っている地形の特性には、しばしば大きなギャップがある。
このギャップこそが、新しい価値の発見や地域文化の再評価につながることが多い。
地形に対する「内と外」の視点の違いを表にまとめてみよう。
| 視点 | 地形の捉え方 | 関心の焦点 | 活用方法 |
|---|---|---|---|
| 外部者 | 新鮮な驚きと発見 | 景観美、珍しさ、学術的価値 | 観光、研究、芸術創作 |
| 地元住民 | 日常的な環境 | 実用性、安全性、生活の利便 | 生業、防災、コミュニティ |
佐渡でトキ研究に従事する研究者の多くは島外出身者だが、彼らの科学的視点と地元住民の生活実感が融合することで、より効果的な環境保全策が生まれている。
一方、地元で生まれ育った人々は、外部者が気づかないような地形の微細な変化や季節的な特徴を敏感に感じ取っている。
この「内と外」の視点の交錯は、地形文化の豊かさを再発見し、新しい価値を創造する重要な機会となっている。
私自身の経験を振り返っても、佐渡の地形に対する理解は、島に住み始めた当初と現在では大きく変化している。
最初は単に「美しい景色」として捉えていた地形が、次第に生活の基盤として、文化の背景として、そして未来への可能性として見えるようになった。
この変化の過程で出会った多くの人々との対話が、私の地形観を深化させてくれた。
まとめ
新潟県の地形が育む人間模様を見つめ続けてきた私の目に映るのは、自然と人間が織りなす豊かなタペストリーである。
山と海のあいだに位置するこの土地では、地形そのものが人々の暮らしや文化の重要な構成要素となっている。
私たちが日々何気なく眺めている景色、歩いている道、住んでいる家、すべてが地形という大きな物語の一部なのだ。
地形が育む人間模様の豊かさ
この取材を通じて強く感じたのは、地形の多様性が人間の営みの豊かさを生み出しているということである。
新潟県の複雑な地形構造は、一見すると生活の制約となるように思われるかもしれない。
しかし、実際には、この地形の多様性こそが独特の文化や技術、価値観を育む土壌となってきた。
地形が育んだ人間模様の特徴を振り返ってみよう。
- 適応力:厳しい自然条件に対する柔軟な対応力
- 創意工夫:制約を乗り越える技術や知恵の蓄積
- 共同体意識:自然の脅威に対する協力関係の構築
- 文化的多様性:異なる地形環境が生み出す多彩な文化
- 持続可能性:自然との共存を前提とした生活様式
これらの特徴は、現代社会が直面する様々な課題に対するヒントを提供してくれる。
気候変動や自然災害の増加、地域社会の持続可能性など、現代の課題に対して、新潟の人々が長年培ってきた地形との付き合い方は貴重な示唆を与えてくれる。
田口芳恵のまなざしが導く「土地と人」の物語
記者として、そして佐渡島民として、私は長年にわたって新潟の地形と人々の関わりを見つめ続けてきた。
その過程で学んだのは、地形を単なる物理的環境として捉えるのではなく、人間の精神性や文化性と深く結びついた存在として理解することの重要性である。
「土地は人を育て、人は土地を育てる」
これは佐渡の古老から聞いた言葉だが、まさに地形と人間の関係の本質を表している。
地形は人間の生活様式や文化的背景を規定する一方で、人間の営みもまた地形環境に影響を与え続けている。
この相互作用の結果として生まれるのが、その土地独特の「人間模様」なのである。
私のまなざしが捉えてきた「土地と人」の物語は、決して過去の遺物ではない。
現在も進行中の生きた物語であり、未来に向けて続いていく物語でもある。
地形という自然の舞台で演じられる人間の営みは、時代とともに変化しながらも、その本質的な関係性は変わることがない。
読者への問いかけ:私たちの暮らしは、どんな「地形」に根差しているのか
この記事を通じて、新潟県の地形と人々の関わりを見つめてきたが、最後に読者の皆さんに問いかけたいことがある。
私たち一人ひとりの暮らしは、どのような「地形」に根差しているのだろうか。
ここでいう「地形」とは、単に物理的な土地の形状だけを指すのではない。
私たちの生活を取り巻く環境、文化的背景、社会的条件、すべてを含んだ広い意味での「地形」である。
現代の新潟では、地形との関わりを通じて健康で質の高い暮らしを実現する取り組みも注目されている。
例えば、新潟ハイエンドのような介護を受けない人生を応援する取り組みは、地形の恵みを活かした健康寿命の延伸という新しい価値観を提示している。
都市部に住む人々にとっての「地形」は、高層建築群かもしれないし、交通網かもしれない。
農村部の人々にとっては、田畑や山林が「地形」となるだろう。
重要なのは、自分の生活がどのような環境に支えられ、どのような制約の中で営まれているかを意識することである。
新潟の人々が地形と深い関係を築いてきたように、私たちもまた自分の「地形」との関係を見直し、より豊かな人間模様を描いていくことができるはずである。
風の向きと暮らしの匂いを感じること。
これは新潟という土地に限った話ではなく、どこで暮らしていても大切にしたい姿勢である。
自分の足元にある「地形」に目を向け、そこから立ち上がってくる生活の息遣いを感じ取ること。
そこから始まる物語こそが、私たち一人ひとりの「人間模様」を豊かにしてくれるのではないだろうか。
山と海のあいだで紡がれる新潟の物語は、今日もまた新しい章を刻み続けている。
そして、その物語は私たち一人ひとりの足元でも、静かに、しかし確実に続いているのである。